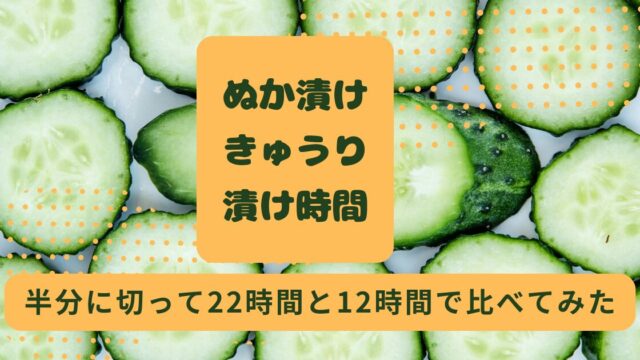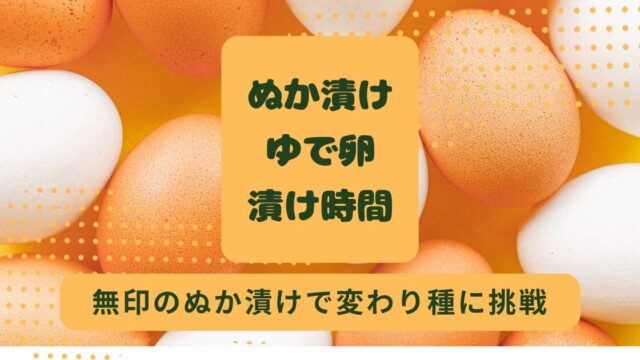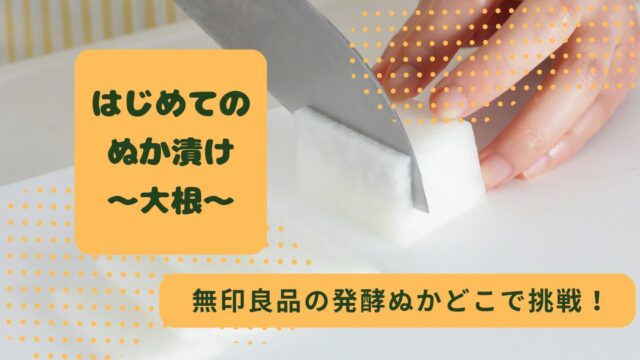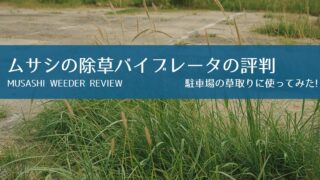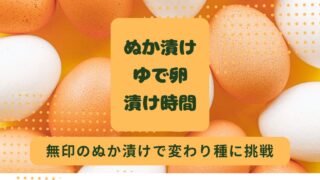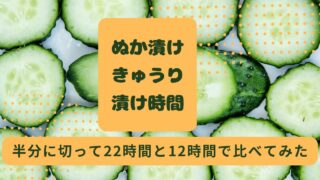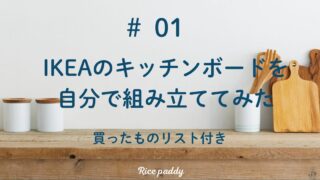手前味噌ができました|味噌づくり3年目の記録

この家で味噌を作るようになったきっかけ
この家に住み始めてから、味噌を自分たちで作るようになりました。
きっかけは、近所のスーパーで開かれていた「味噌の仕込み講座」。
子ども連れでも参加できるということで、気軽に申し込みました。
味噌は発酵食品の一つで、私たちの生活にとても馴染みのある食材です。
私自身の美術作品のテーマである「保存」にも通じる部分があり、以前から興味がありました。
さらに子どもの食育にもなるなと思い、一石三鳥の体験でした。
味噌の仕込み手順
ここでは、私が実際に毎年行っている味噌の仕込み方法を簡単にまとめます。
材料
- 大豆
- 米麹
- 塩
作り方
- 塩と米麹を混ぜ合わせる。
- 煮て柔らかくなった大豆をしっかり潰す。
- 潰した大豆と塩麹を混ぜ合わせる。
- 保存容器に空気が入らないように詰める。
- 表面をならして重石をのせる。
- あとは待つだけ。
味噌の仕込みはいつも2月頃に行っています。
手作り味噌キットとの出会い
ありがたいことに、講座を開いてくれていたスーパーが
毎年「味噌手作りキット」を販売してくれています。
このキットのおかげで、何も考えずに材料をそろえられる手軽さがあり、
ズボラな私でも続けられているのだと思います。
味噌手作りキットに付いていた容器。毎年使えます。
豆もすでに煮てあるので、潰す作業のみ。ありがたい〜!
麹と塩、そして我が家の菌たち
豆を潰し、米麹と塩を混ぜ合わせます。
麹は生き物なので、扱いに少し注意が必要です。
購入時の説明によると、すぐに仕込まない場合は冷凍保存を。
寒さで麹の活動を止めておくためだそうです。
大豆・麹・塩を混ぜ合わせるとき、
家の中の菌や手の常在菌が加わり、オリジナルの味噌が生まれます。
世界に一つだけの味噌です。
言葉にすると少し驚かれるかもしれませんが、
それも「発酵の面白さ」の一部だと感じます。
仕込みの仕上げと重石の工夫
味噌を容器に詰め、空気を抜きながら表面をならします。
重石を乗せれば仕込み完了!
我が家では2kgの重石が必要なのですが、
近所のホームセンターには1.5kgのものしかなく、
残りの500gは塩をジップロックに入れて代用しています。
半年ほど待てば完成。
放っておくだけで味噌ができるなんて、なんてすばらしい発酵文化でしょう。
2025年の味噌の出来あがり
仕込んでから3か月ほど経った頃に、「あがり(上澄み液)」の様子を確認します。
3回とも問題なく発酵が進み、重石の調整も不要でした。
もし「あがり」が少ない場合は、重石を少し増やす必要があります。

失敗から学んだこと
初めての年は、冷凍庫に横向きでタッパーを入れてしまい、
「あがり」が漏れて大惨事に。以後、ポリ袋に入れるようにしています。
また、重石代わりに使った塩に「あがり」が染み込み、
去年と今年はその塩をダメにしてしまいました。
湿った塩の再利用方法については、今後調べてみたいと思っています。
2026年への抱負
来年もまた、2月になったら仕込みたいと思います。
今度はキットではなく、自分で材料を集めてみたい。
時間はかかるけれど、豆を煮るところからやってみたい。
丁寧に向き合うことで、味噌の深みがもっと感じられそうです。
まとめ
- 味噌づくりは手軽に始められる発酵の楽しみ
- 続けることで、年ごとの違いを味わえる
- 失敗も含めて、暮らしの記録になる
来年も、手前味噌の季節が楽しみです。